

「児童福祉施設による里親支援のあり方の調査研究事業報告書」を読んでの考察
この調査は、平成15年8月から9月にかけて、全国の里親及び児童養護施設・乳児院に対して行われました。本書は、「児童福祉施設による里親支援に関する調査」と「里親支援を実施している児童福祉施設に対する訪問調査」の二つの調査により報告書がまとめられていす。
1.回収率(報告書p19)
アンケートの回収結果は、里親が送付数2023名に対し、1203名の回収(59.5%)と、個人に対する調査としては、かなり大きな回収率となっています。通常の個人アンケートでは3割の回収率で成功と言われていますが、6割もの回収率は、本調査への里親の期待の高さが伺われます。
また、児童養護施設は送付数551で回収率69.3%です。3割もの児童養護施設が、組織として回答しないことを決定したのであれば、残念な気がします。しかし、乳児院は、送付数115で回収率85.7%となっています。それぞれの回収率に、児童福祉施設と里親の温度差が感じられます。
|
|
回収率 |
|
児童養護施設 |
69.3% |
|
乳児院 |
85.7% |
|
里親 |
59.5% |
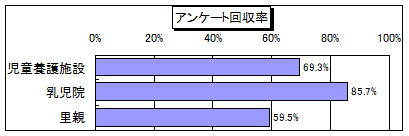
2.里親と児童養護施設の関わりの有無(報告書p22)
3年間の間、里親との関わり(措置変更したケース、里親委託を前提に交流したケースなど)があった施設は、養育里親は37.2%、季節里親・週末里親69.0%と、養育里親より季節里親・週末里親との関わりが多い。施設にとっては、施設に籍を置いたまま、家庭体験事業としてボランティア里親が必要とされているのではないか。
|
|
あった |
なし |
N.A. |
合計 |
あった |
なし |
N.A. |
合計 |
|
養育里親 |
139 |
225 |
10 |
374 |
37.2% |
60.2% |
2.7% |
100% |
|
季節・週末里親 |
258 |
108 |
8 |
374 |
69.0% |
28.9% |
2.1% |
100% |
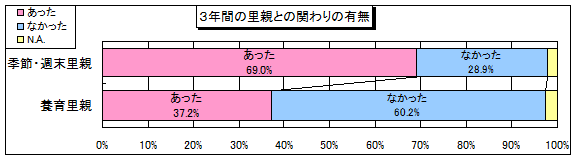
3.児童養護施設からの養育里親委託の有無(報告書p22)
平成12年度から14年度に児童養護施設から里親委託があった施設の割合は、6.7%(12年度)、10.7%(13年度)、12.6%(14年度)と増えてきたが、80.7%(14年度)の児童養護施設では、里親委託がなされていない。
●児童養護施設における養育里親委託の有無
里親委託のある施設でも、里親委託が年間に一人の施設が33施設(70.2%)、年間5人以上里親委託している養護施設が1施設(2.1%)あった。|
年 度 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
|
平成12年度 |
321 |
25 |
28 |
374 |
85.8% |
6.7% |
7.5% |
100% |
|
平成13年度 |
305 |
40 |
29 |
374 |
81.6% |
10.7% |
7.8% |
100% |
|
平成14年度 |
302 |
47 |
25 |
374 |
80.7% |
12.6% |
6.7% |
100% |
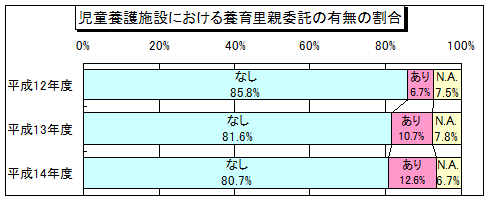
●児童養護施設における養育里親への委託人数別内訳
|
年度 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人以上 |
合 計 |
|
平成12年度 |
18 |
6 |
0 |
1 |
0 |
25 |
|
平成13年度 |
30 |
8 |
2 |
0 |
0 |
40 |
|
平成14年度 |
33 |
10 |
2 |
1 |
1 |
47 |
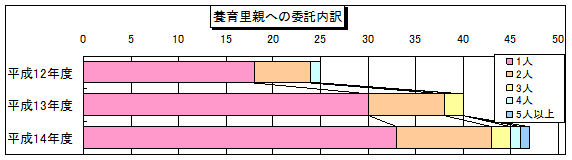
4.児童養護施設からの養子縁組里親委託の有無
養子縁組を前提とした里親委託は、平成14年度で19施設(5.1%)でした。
●児童養護施設における養育里親委託の有無
養子縁組里親への委託がある養護施設でも、年間に1人委託している養護施設が16施設(84.2%)、年間2人委託している養護施設が3施設あった。
|
年度 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
|
平成12年度 |
325 |
21 |
28 |
374 |
86.9% |
5.6% |
7.5% |
100% |
|
平成13年度 |
332 |
16 |
26 |
374 |
88.8% |
4.3% |
7.0% |
100% |
|
平成14年度 |
330 |
19 |
25 |
374 |
88.2% |
5.1% |
6.7% |
100% |
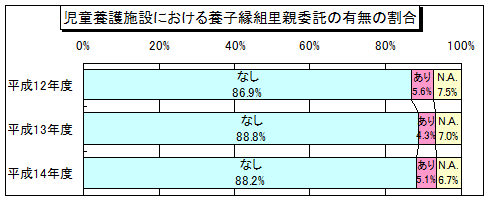
●児童養護施設における養子縁組里親への委託人数別内訳
平成11年4月30日付児発第420号厚生省児童家庭局長通知「里親活用型早期家庭養育促進事業の実施について」では、「児童養護施設等入所児童で、父母が死亡した児童や父母が長期にわたって行方不明である児童等家庭への復帰が困難な児童については、里親委託措置等に努めるようお願いしているところであるが、今般、『里親活用型早期家庭養育促進事業実施要綱』を別紙のとおり定め、児童養護施設等入所児童のうち、里親委託が望ましい児童については、施設の援助のもと積極的に里親委託を実施し、児童の自立支援を図ることとしたので、その適正かつ円滑な実施を期せられたく通知する。」と、各都道府県知事・各指定都市市長あてに通知しています。
この通知が児童相談所及び児童養護施設に理解され、実施されているのでしょうか。
|
年度 |
1人 |
2人 |
合計 |
|
平成12年度 |
18 |
3 |
21 |
|
平成13年度 |
14 |
2 |
16 |
|
平成14年度 |
16 |
3 |
19 |
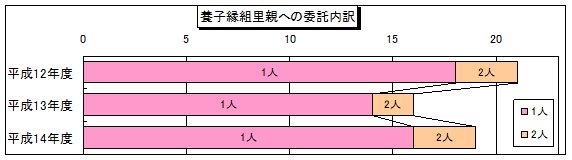
5.児童養護施設における季節里親・週末里親の状況
里親委託は、児童相談所の措置権や実親の意向が絡むため、児童養護施設だけでは難しいのですが、施設単独で行うことのできる週末・季節里親については、回答した施設の46.8%(14年度)で行っています。在籍児童に占める週末・季節里親の率が80%を越える施設もあります。千葉県の恩寵園では、季節里親は最高の第三者機関であるとして、積極的に週末・季節里親に出していますが、子どもに家庭生活を体験させ、将来の家庭のイメージを持たせるためにも、施設側の積極的な取り組みを期待したいです。
●児童養護施設における季節里親・週末里親の状況
|
年度 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
|
平成12年度 |
192 |
152 |
30 |
374 |
51.3% |
40.6% |
8.0% |
100% |
|
平成13年度 |
182 |
164 |
28 |
374 |
48.7% |
43.9% |
7.5% |
100% |
|
平成14年度 |
174 |
175 |
25 |
374 |
46.5% |
46.8% |
6.7% |
100% |
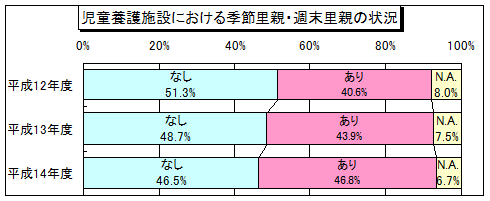
●児童養護施設における季節里親・週末里親の人数別内訳
ただ、里親委託へのステップではなく、単なる「家庭体験事業」の位置づけであるのであれば、画餅となりかねません。どのような位置づけで、週末・季節里親を行っているのか知りたいところです。
一昨年の制度改正で、長期委託につなげることを期待して里親制度(短期里親)に組み込まれた週末・季節里親ですが、今回の調査では、里親委託(措置変更)につながったケースが不明です。是非、次回の調査では取り組んでほしい項目です。
|
年度 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
10人〜 |
20人〜 |
合計 |
|
平成12年度 |
18 |
27 |
14 |
13 |
13 |
32 |
26 |
9 |
152 |
|
平成13年度 |
17 |
25 |
18 |
21 |
10 |
38 |
29 |
6 |
164 |
|
平成14年度 |
27 |
26 |
13 |
18 |
14 |
43 |
27 |
7 |
175 |
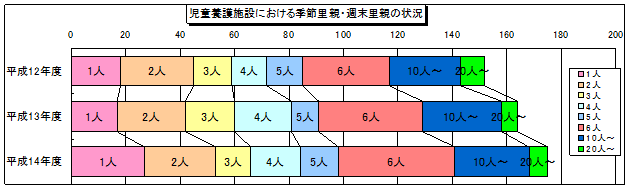
6.里親と乳児院の関わりの有無
乳児院では、養育里親委託が29%(14年度)、養子縁組里親委託が56%(14年度)と、乳児院の数では比較多いものの、里親委託が0の乳児院が少なくない率であるのは「乳幼児は原則里親委託」を求めている里親として、残念な気持ちです。
●里親と乳児院の関わりの有無
|
|
あった |
なかった |
N.A. |
合計 |
あった |
なかった |
N.A. |
合計 |
|
養育里親 |
63 |
28 |
9 |
100 |
63.0% |
28.0% |
9.0% |
100% |
|
養子縁組里親 |
44 |
10 |
46 |
100 |
44.0% |
10.0% |
46.0% |
100% |
|
季節・週末里親 |
9 |
87 |
4 |
100 |
9.0% |
87.0% |
4.0% |
100% |
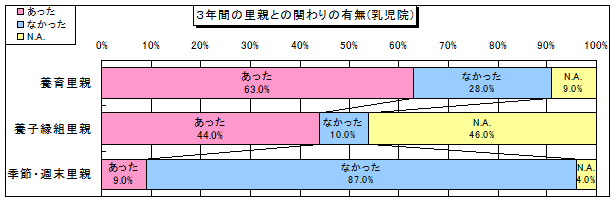
7.乳児院からの養育里親委託の有無
●児童養護施設における養育里親委託の有無
平成12年度から14年度に乳児院から里親委託があった施設の割合は、19.0%(12年度)、28.0%(13年度)、25.9%(14年度)と増えてきたが、58.9%(14年度)の乳児院では、3年間のあいだ里親委託がなされていません。
|
年度 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
|
平成12年度 |
75 |
19 |
6 |
100 |
75.0% |
19.0% |
6.0% |
100% |
|
平成13年度 |
67 |
28 |
5 |
100 |
67.0% |
28.0% |
5.0% |
100% |
|
平成14年度 |
66 |
29 |
17 |
112 |
58.9% |
25.9% |
15.2% |
100% |
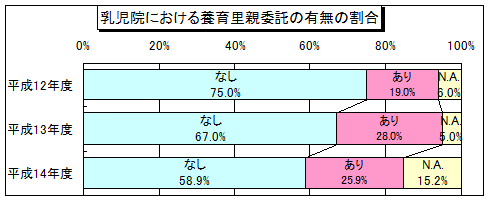
●児童養護施設における養育里親への委託人数別内訳
里親委託のある乳児院では、平成14年度で里親委託が年間に1人の乳児院が17施設(58.6%)、5人以上里親委託している乳児院が4施設(13.8%)ありました。|
年度 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人〜 |
合計 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人〜 |
合計 |
|
平成12年度 |
7 |
3 |
6 |
0 |
3 |
19 |
36.8% |
15.8% |
31.6% |
0.0% |
15.8% |
100% |
|
平成13年度 |
14 |
5 |
5 |
1 |
3 |
28 |
50.0% |
17.9% |
17.9% |
3.6% |
10.7% |
100% |
|
平成14年度 |
17 |
5 |
3 |
0 |
4 |
29 |
58.6% |
17.2% |
10.3% |
0.0% |
13.8% |
100% |
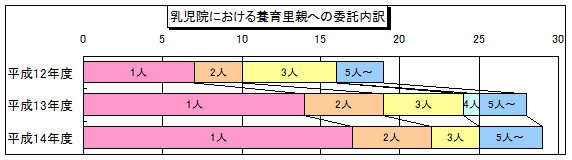
8.乳児院からの養子縁組里親委託の有無
平成12年度から14年度に養子縁組里親委託があった乳児院の割合は、58.0%(12年度)、52.0%(13年度)、56.0%(14年度)と変わらない。40.0%(14年度)の乳児院では、3年間のあいだ養子縁組里親委託がなされていません。
●乳児院における養子縁組里親委託の有無
|
年度 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
なし |
あり |
N.A. |
全体 |
|
平成12年度 |
35 |
58 |
7 |
100 |
35.0% |
58.0% |
7.0% |
100% |
|
平成13年度 |
42 |
52 |
6 |
100 |
42.0% |
52.0% |
6.0% |
100% |
|
平成14年度 |
40 |
56 |
4 |
100 |
40.0% |
56.0% |
4.0% |
100% |
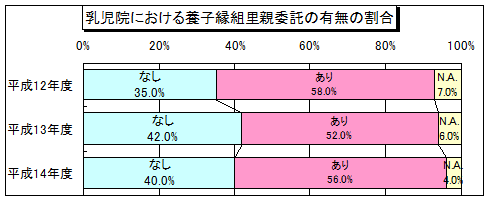
●乳児院における養子縁組里親への委託内訳
養子縁組里親への委託に熱心な乳児院では、一人だけでなく積極的に子どもを養子縁組里親にだしていることが伺えます。
各年度3月1日現在に、季節里親・週末里親のいる児童がいた乳児院は、平成14年度で4か所(4.0%)にすぎませんでした。乳児院においては、季節里親・週末里親をどのように位置付けるのか、その意義が不明であり、数も少ないことから、ここでは論評しません。
|
年度 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人〜 |
合計 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人〜 |
合計 |
|
平成12年度 |
24 |
15 |
9 |
6 |
4 |
58 |
41.4% |
25.9% |
15.5% |
10.3% |
6.9% |
100% |
|
平成13年度 |
21 |
7 |
15 |
5 |
4 |
52 |
40.4% |
13.5% |
28.8% |
9.6% |
7.7% |
100% |
|
平成14年度 |
18 |
16 |
7 |
9 |
6 |
56 |
32.1% |
28.6% |
12.5% |
16.1% |
10.7% |
100% |
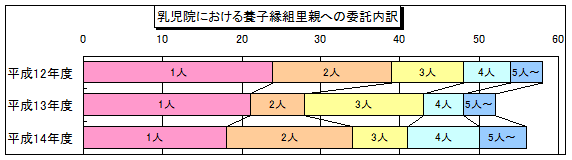
9.乳児院退所児童に占める養育・養子縁組里親への措置変更児童の割合、施設定員別平均値
乳児院退所児童に占める養育里親への措置変更児童の割合は、平成13年度、14年度ともに20人未満の乳児院では、いずれも10%以上です。20人以上の乳児院は、20未満の乳児院の半分以下です。80人以上の規模の乳児院では、平成14年度の養育里親委託・養子縁組委託が0となっています。80人規模の施設では、たった一人の委託があっても、1%になるわけですから、全然委託が無かったということなのでしょうか。
20人未満の乳児院では、子どもに目が届く分、養育里親への委託に熱が入るのでしょうか。
●乳児院退所児童に占める養育里親への措置変更をした児童の割合、施設定員別平均値
|
年度 |
サンプル数 |
平均値 |
20人未満 |
20人〜 |
40人〜 |
60人〜 |
80人〜 |
|
平成12年度 |
93 |
2% |
5% |
2% |
2% |
2% |
1% |
|
平成13年度 |
93 |
4% |
10% |
2% |
4% |
4% |
3% |
|
平成14年度 |
93 |
4% |
11% |
2% |
3% |
5% |
0% |
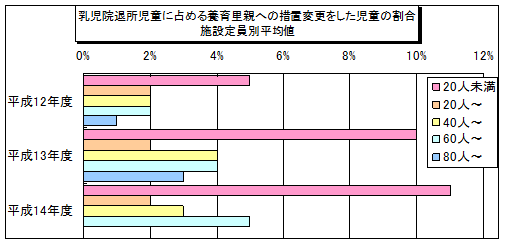
乳児院退所児童に占める養子縁組里親への措置変更児童の割合は、養育里親のそれよりも3〜4%高いです。20人未満の乳児院では、20人以上の乳児院に比べて、養子縁組委託が高い傾向があります。
20人未満の乳児院では、子どもに目が届く分、養育里親及び養子縁組里親への委託に積極的なのでしょうか。
●乳児院退所児童に占める養子縁組里親への措置変更をした児童の割合、施設定員別平均値
|
年度 |
サンプル数 |
平均値 |
20人未満 |
20人〜 |
40人〜 |
60人〜 |
80人〜 |
|
平成12年度 |
92 |
6% |
10% |
7% |
4% |
2% |
5% |
|
平成13年度 |
92 |
6% |
6% |
7% |
5% |
1% |
7% |
|
平成14年度 |
94 |
7% |
16% |
7% |
4% |
3% |
7% |
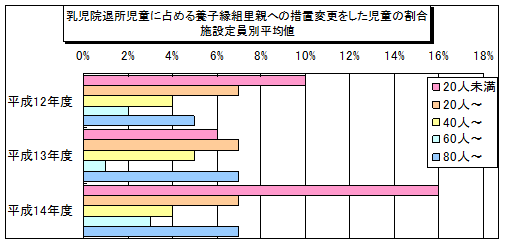
里親委託をした児童福祉施設が数少ない中で、児童福祉施設による里親支援のあり方を検討するのも大切ですが、児童福祉施設から里親への委託数をどう増やすのか、特に、人間としての基本的信頼関係を築く、人生の一番大切な0〜3歳の時期を、どのような環境で過ごすのか、その調査研究も必要だと思います。
10.里親制度についての認知・関心
里親制度についての認知・関心は、児童養護施設、乳児院共に、施設長の方が職員より里親制度に関する認知や関心が高い傾向が同様に見られました。「平成14年度の里親制度の改正」は、「非常によく知っている」「ある程度知っている」を合わせて89.2%、「欧米では施設養護より里親委託が普及している」は93.7%と、いずれも高い数値を示しました。乳児院でも、前者が94.6%、後者が91.4%と同じように高い数値でした。
施設と里親のパートナーシップ(協力関係)については、養護施設が「非常に必要だ(42.6%)」「ある程度必要だ(46.3%)」と合わせて88.9%、乳児院が「非常に必要だ(51.6%)」「ある程度必要だ(39.8%)」と合わせて91.4%と、いずれも高い数値でした。
施設と里親がパートナーシップを結ぶメリットは、養護施設は、「児童の家庭生活体験(64.9%)」「里親促進による児童のパーマネンシー保障(21.9%)」の数字から、施設養護を補完する週末・季節里親への役割を求めている印象を受けました。乳児院では、「児童の家庭生活体験(40.3%)」「里親促進による児童のパーマネンシー保障(39.8%)」と、パーマネンシー保障がメリットとして養護施設より高い数値を示しているのが対照的です。
(註:パーマネンシー…永続的信頼関係)
里親への要望は、養護施設では「ある(28.2%)」「ない(25.8%)」、乳児院では「ある(44.1%)」「ない(14.0%)」と、乳児院のほうが里親への要望が高いのが特徴的でした。主な内容は、「養育里親の増加・開拓」「被虐待児の学習・理解」「里親としての専門性の向上」「子どもへの過干渉・過度な期待をしない」「普通の生活をさせて欲しい」でした。
中には、「年長児の里親が必要だ」との意見もありますが、「児童養護施設入所児童等調査結果の概要(平成15年2月1日厚生労働省調査)」によると、入所時・委託児の児童の年齢は、15歳(里親2.1%、施設1.6%)、16歳(里親1.4%、施設0.5%)、17歳(里親0.7%、施設0.2%)と、比率にすると若干ですが、施設より里親のほうが高齢児を受けている率が高いです。または、施設児童の自立準備としての役割を、里親に求めているのかも知れません。
「里親委託が普及することが児童の最善の利益につながると思うか」については、養護施設が「おもう(47.7%)」「思わない(2.0%)」「どちらともいえない(46.7%)」、乳児院が「おもう(48.9%)」「思わない(3.2%)」「どちらともいえない(44.1%)」と、ほぼ同じ傾向を示しました。公式回答であるため、「思わない」が極端に少なく、「どちらともいえない」という数字の中に、施設の戸惑いが感じられます。「どちらともいえない」理由については聞かなかったとのことで、是非とも、聞いて欲しかった項目でした。
いずれにせよ、アンケートの回答数の半数近い養護施設・乳児院が「里親委託を児童の最善の利益」と考えていることは、嬉しいと思う反面、残り半数の施設に対する里親制度の理解を求めていく必要を感じました。
現時点でのまとめ
最後の考察とまとめでは、「1.児童福祉施設による里親支援の実態と意識」として、児童養護施設では養育里親への委託よりも、季節里親・週末里親との関わりが多く、より積極的な取り組みが見られた。季節里親・週末里親を利用することの子どもへのメリットもあると認識する回答が多かった。
養護施設や乳児院が里親に提供できる研修内容と、里親側が求めている研修内容や相談内容が合致していることからも、相互に連携することが望ましいとしています。
そして、児童福祉施設も里親も互いに向き合おうとする姿勢を読み取ることができるとしています。
「2.これから始まる里親と児童福祉施設の新たな関係づくりへの課題」では、キーワードとして、「自己理解」「パートナーシップ」「キーパーソン」「子ども主体」の4つをあげています。
「自己理解」では、里親には、「子どもを自子として育てる『親』ではなく、『社会的養護を担う存在』であるという自己理解を深め、それに沿った養育をすることが求められる」とし、児童福祉施設には、「施設に入所している子どもやその家庭のみではなく、地域に開かれた支援を提供する『専門職集団』であるとの自己理解が求められている」としている。
「パートナーシップ」では、「同じ社会的養護を担うものとしての自己理解の次に、相互理解に基づくパートナーシップが重要である」としています。
「キーパーソン」では、「児童福祉施設の施設長とともに活躍するキーパーソンの存在が必要」としている。
「子ども主体」では、「生来の家庭・里親・児童福祉施設、このいずれの養育環境が『子どもにとって』ふさわしいのかという視点から、社会的養護を提供していくことが今後の課題である。同じ社会的養護を担うものとして、ともに対等な選択肢として共存し連携していくようにすることが今後必要ではないか」としています。
しかし、
「また、社会的養護に置かれる子どもには、この選択肢のほかに、『居場所』を確保していくことが重要である。現状では、子どもが里親委託された時点で児童福祉施設や居住していた地域で培っていた人間関係が切れてしまうということが多い。乳児院から里親委託された子ども、児童福祉施設を経ずに里親委託された子どもはどこへ帰ればいいのだろうか。また、社会的養護の年齢制限後に、自分の居場所と認識できる場所へ帰ることのできる子どもはどの程度いるであろうか。子どもを主体とする支援を提供するためには、地域づくりとともに、子どもの居場所づくりも今後の課題である(※傍線は筆者)」
との文章には、疑問を禁じ得ません。里親制度を知らないものが書いたとしか思えません。
この「子どもが里親委託された時点で児童福祉施設や居住していた地域で培っていた人間関係が切れてしまうということが多い」という記述は正しくありません。まず、実親家庭から児童福祉施設に措置された時点で、子どもの地域・友達・学校の関係が断ち切られます。親が育てられなくなった子どもは、家庭を失うだけでなく、学校の友達を失い、地域の関わりを失い、知る人もいない遠く離れた児童福祉施設に一人で入所するのが現状です。ですから、私たち里親は、親が育てられなくても、施設ではなく地域の里親家庭で育ち、せめて地域や学校の友達関係は継続させたいと願い、「小学校区に一つ以上の里親家庭を!」と運動しています。
「乳児院から里親委託された子ども、児童福祉施設を経ずに里親委託された子どもはどこへ帰ればいいのだろうか」との記述も、まるで、乳児院から里親委託をされた子ども、家庭から直接里親委託をされた子どもには、「帰る場所」が無いと言わんばかりの表現です。私たち里親は、子どもの「帰る場所」として家庭で育てます。また、乳児院が「帰る場所」とならないように、「乳幼児は原則里親委託」を要求しています。子どもにとって「帰る場所」とは、子どもが集団で暮らし養育者が交代勤務で変わる施設ではなく、自分だけの大人が育ててくれる家庭なのです。
「また、社会的養護の年齢制限後に、自分の居場所と認識できる場所へ帰ることのできる子どもはどの程度いるであろうか」についても、里親家庭で育つ子どもは、里親家庭を「居場所」として育ち、自立したあとも、里親家庭を実家として帰ってきます。心の絆を法的な絆に広げたいと、養育里親から養子縁組をされる里親子もいます。
平成16年7月10、11日に箱根で開催された関東甲信越静里親研究協議会では、里親家庭を巣立った子ども達がパネラーとして発言しました。その席において、里親家庭で育った方たちに「居場所はどこですか」と質問したところ、「里親家庭です」と迷いなく答えて下さいました。さらに、「物心つく前に乳児院から里親家庭に行きたかった」とも言って下さいました。養護施設で育った方は、居場所については迷いながら、とうとう答えることが出来ませんでした。
生後すぐに乳児院に入り、2才10ヶ月で里親家庭に行った子どもが半年ほど経って里親に言いました。「おとうさん、なんではやくむかえにこなかったの」と。その里親は、子どもを抱きしめ、泣きながら子どもに謝ることしか出来ませんでした。子どもの「居場所」は、家庭以外にあるのでしょうか。
最後に、「この推進のため、来年度から里親と児童福祉施設のパートナーシップを図るための委員会づくりも企画されている。この委員会では里親と児童福祉施設の合同研修のあり方など、具体的な検討がなされる予定である。こういった歩み寄りは、今後の里親と児童福祉施設の新たな関係づくりの新たな一歩になると考えられる。」と締めくくっています。
しかし、「どのような環境で育つのが子どものためになるのか」、「子どもの家庭で育つ権利をどう保障するのか」、「子ども時代の全てを施設で過ごす子がいる現状をどうするのか」など、社会的養護の理念を確立せずに、里親と児童福祉施設のパートナーシップを図っても、子どもが置き去りにされていきます。理念無きパートナーシップは、単なる談合になりかねません。
誰のためのパートナーシップなのか、何のためのパートナーシップなのか、社会的養護の基本理念を見定めながら、パートナーシップのあり方を議論すべきでしょう。
さて、今回のアンケートは、1203名の里親と390か所の児童養護施設、100か所の乳児院が回答して下さいました。しかし、報告書は、全国の養護施設・乳児院と、都道府県政令市の児童家庭課に送られ、里親へは、都道府県政令市里親会のみに送られました。本来、アンケートに回答した全里親に送るべきものですが、予算の都合で送ることが出来なかったと、事務局(全国社会福祉協議会)からの回答があり、その代わりとして、電子化した報告書をいただきました。
そこで、本報告書の全文(118ページPDFファイル510KB)をアップしました。どうぞ、ダウンロードし、全文をお読みいただければと思います。
2005年6月
文責:sido 東京都養育里親
Sidoさんの里親資料室 http://foster-family.jp/data-room/zenshakyo/200402satooya-shien.pdf